Hi、ハチワレ猫×2とふらまめです。
窓を開けると、心なしか風が春の匂い。 猫たちは相変わらず丸くなっているので、夫とふらり近所の公園まで散歩に。
ここには、戯曲『女の一生』の原作者・森本薫の碑がひっそりと建っています。


「誰が選んでくれたのでもない、自分で選んで歩き出した道ですもの、間違いと知ったら自分で間違いでないようにしなくちゃ」
ここの前を通るたび、私はこの有名なセリフを口に出して真似をしたくなる。
そう、杉村春子になったつもりで。
けれど、隣にいた夫がキョトンとした顔でこう言うのだ。 「杉村春子って、そんなに有名なん?」

うううむ
そうか、演劇に興味がない人間には「昔の女優さん」のうちのひとりだよなあ。かく言う私だって晩年の姿しか知らないし。杉村春子を覚えてるって人も少なくなっているのかなあ。 若い世代はもっと知らないよなあ。そうだよなあ。
家に戻り本棚を漁ると、あの公演パンフレットが出てきました。
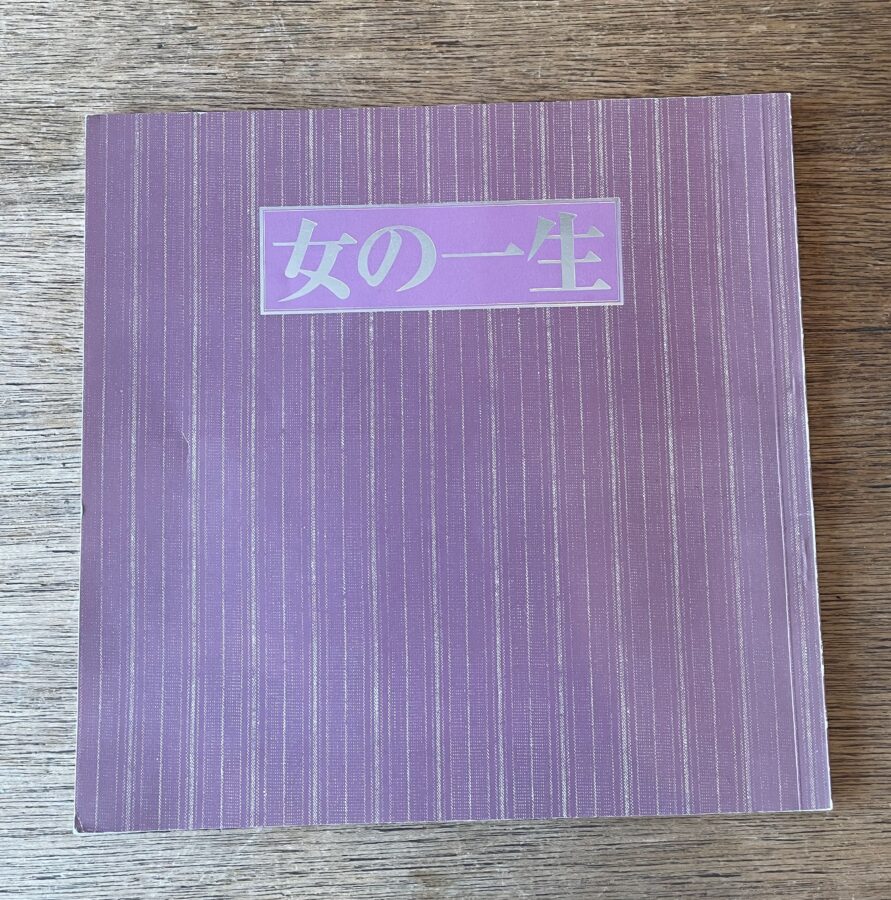


うーなんだか昔話がしたくなってきた。
平成元年。バブル真っ只中。東京・池袋のサンシャイン劇場10周年記念公演。そして「女の一生」800回記念公演。当時20代でお金のなかった私は、当日券の立ち見に並びました。
当時はアングラ劇団や学生劇団が全盛期。 新劇の舞台はチケット代が高くてなかなか手が出せなかったけれど、「この作品だけは、無理してでも今、観ておかなければ」と直感したのを覚えています。
物語の背景は、日露戦争後から昭和初期。商家の柱として気丈に家を守り抜く女性の一生。 当時すでにかなりのご高齢だった杉村春子さんが、16歳の少女から60代までを一気に演じきる。 幕が上がってから下りるまで、彼女の圧倒的な存在感が舞台を支配し続けていました。
パンフレットを読み返して、何より驚くのがその「初演」。昭和20年4月、東京・渋谷。 終戦間近、空襲警報が鳴り響く中での上演。 「戦地に向かう前に、もう一度だけ芝居がしたい」 そんな覚悟で集まった人々が作った作品だったそうです。
杉村春子といえば「文学座の顔」であり、「演劇界のドン」のような厳しくて怖そうなイメージもあるけれど、あの佇まいは、激動の時代を生き抜いてきた表現者のプライドと自信の現れだったのでしょう。
思い出は連鎖して_。ちょうどそのころ、信濃町の「文学座アトリエ公演」も観に行ったことがあります。 木造のなんとも言えない趣がある稽古場。 演目はたしか、チェーホフの『桜の園』。

観客は年配の方ばかりわずか10人ほど。 ロシア文学特有の、あの(陰鬱で、どこか諦念の漂う)空気感。 古い木造建物の匂いと相まって、背伸びして「大人の世界」を覗きみたような不思議な高揚感を感じました。
あれから長い月日が流れて、一昨年。 尼崎のピッコロシアターで久々に文学座の公演を観ました。 舞台美術家・朝倉摂の物語。どっしりと安定した演技力、見ごたえのある舞台。そこにはあの杉村春子が形作った文学座の「芯の太い芝居」が、確かに受け継がれていました。
ふう。 とりとめもなく昔話をしてとてもスッキリしました。 たまには、記憶の箱をひっくり返すのも悪くありませんね。
さて、今日は少し丁寧に淹れたお茶でも飲んで、猫たちとゆっくり過ごそうっと。では。

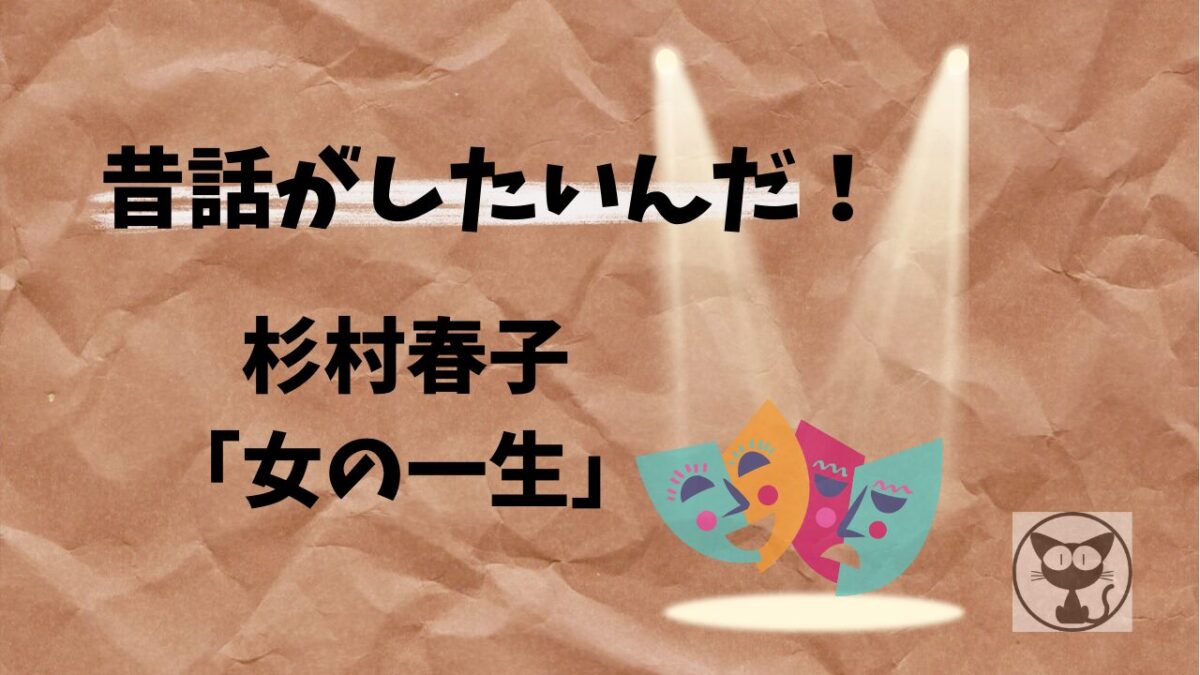

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます